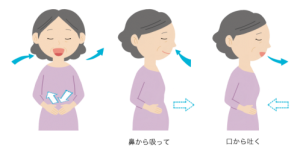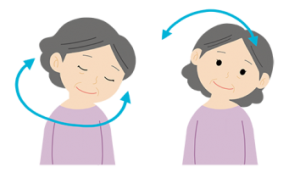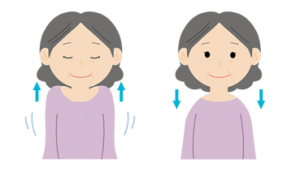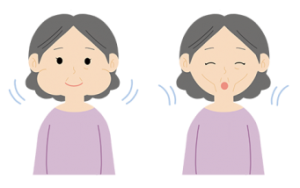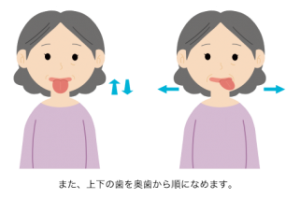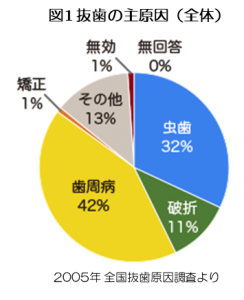すっかり寒くなって、なかなか布団から出られないふうちゃんです
年末が近づき、クリスマスや忘年会など、お酒を飲む機会が増えるのではないでしょうか?
「メタボを予防・改善していこう!」のコラムでは、「お酒は飲みすぎない」という紹介がありましたが、なぜお酒はメタボと関係しているんでしょうか?
メタボの診断には、肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病が指標となりますが、これらの生活習慣病を引き起こす原因として、お酒の飲みすぎも1つの原因であるとされています
それぞれのアルコールとの関係性について見ていきましょう。
・肥満
唐揚げやポテトチップスなど、お酒のつまみについつい何か食べたりしていませんか?
アルコールは、食欲を亢進する作用があるため、食事が進みやすくなります。そのため、お酒に含まれるエネルギーだけでなく、おつまみによってエネルギーや脂質の摂取量が増え、肥満へとつながります。
・高血圧
お酒の量が多くなるほど、高血圧になることが多いことが報告されています。
・脂質異常症
飲酒によって中性脂肪が増加しやすいため、脂質異常症と関連しています。
・糖尿病
肥満と同じで、お酒によって食事量が増えやすいことや、アルコール性の肝臓病・膵臓病によって糖尿病になることもあります。
では、メタボ予防にはお酒の量はどれくらいだといいのでしょうか?
国民の健康施策である「健康日本21」では、飲酒量は男性で純アルコール20g程度までとされています。これは缶ビール(350ml)約1本分に当たります。
また、週に2日間の休肝日を作ることも大切です。
付き合いでお酒を飲まれる方や、お酒好きの方にはハードルが高いかもしれませんが、自分の健康を考え少しずつでも改善していきましょう!
〈参考〉
アルコールとメタボリックシンドローム / 厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-01-005.html