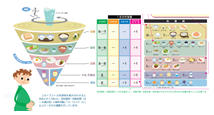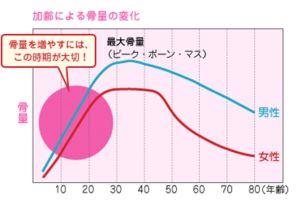三大栄養素~脂質編~
こんにちは!今回のコラムはおぎゃわがお送りします。
最近、歳のせいか胃もたれが酷いです。
歳と言ってもまだ若いのですが、脂っこいお肉や揚げ物、ショートケーキを沢山食べると胃もたれしてしまいます。高校生の頃はスイーツ食べ放題に行ったり、部活終わりにコロッケや唐揚げを食べてもなんともなかったのに、少し悲しい気持ちです。
本日はそんな揚げ物やお肉の脂身に沢山含まれる三大栄養素の1つである脂質についてお話しします!
みなさん脂質と聞くと
「油!カロリーが高い!」
「食べたら太る!」
そんなイメージがあるかもしれません。
しかし、脂質も三大栄養素の一つ、なくてはならない栄養素なんです!
脂質とは、水には溶けない化合物です。
脂質は油やバター、マーガリン、肉の脂身などに多く含まれます。
体内でエネルギー源として、また細胞膜を作る成分として働きます。
食事から摂取する脂質は多すぎても少なすぎても健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
脂質は同じ重さで比べると、炭水化物やたんぱく質よりも大きなエネルギーを持っていて、脂質を取りすぎると特に運動不足の場合にはエネルギーのとりすぎとなります。
摂りすぎたエネルギーは体脂肪として蓄積されるため、肥満やメタボリックシンドロームの原因となります。
一方、脂質の摂取が不足するとビタミンの吸収を悪くしたり、エネルギー摂取不足になりやすくなったりします。
ではどのくらい脂質を摂ればいいのでしょうか?
日本人の食事摂取基準では1日に脂質を
12〜14歳では男子が60g女子が55g
15〜17歳では男子が65g女子が55g
摂取する事が推奨されています。
重さ(g)だけ言われてもさっぱり!想像出来ない!そんなあなたに分かりやすく食品の脂質の量をお教えします!
★かつ丼32.5g
★ハンバーガー大30.4g
★カレーライス24.9g
★ドーナツ(1つ)14.7g
★ショートケーキ14g
★ポテトチップス(1袋)10.5g
★ラーメン4.0g
★おにぎり0.3g
いかがでしたか?カレーライスやハンバーガーの大は1日の約半分の脂質量が含まれていることがわかります。お菓子やファストフードは脂質の多いものが多いです。
食品にどのくらい脂質まれているのかを確認して脂質のとり過ぎに注意してみてくださいね!

.png)
1.png)
2.png)